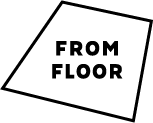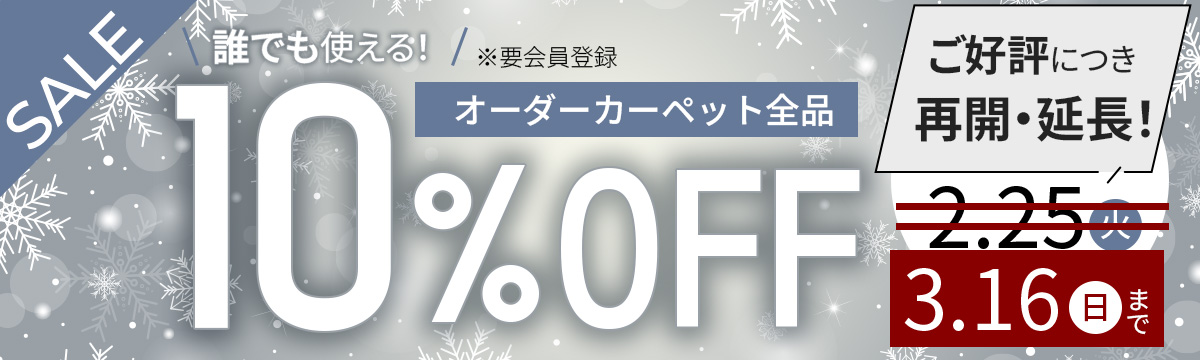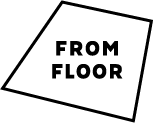梅雨時など雨が続くと、ラグやカーペットが湿気を帯びてしまうことがあります。
カーペットを湿気を放置しているとカビやダニ、臭いの原因になるため注意が必要です。
このようなトラブルを回避するためにも、お部屋の換気やカーペットの陰干しは積極的に行いましょう。
除湿シートを敷いたり、予め調湿性の高いカーペットを選んだりすることで、湿気によるカーペットのトラブルを減らすことができます。
本記事ではカーペットの湿気対策について解説いたします。
湿気が多いと発生しやすいカーペットのトラブル

湿気が多いと発生しやすいカーペットのトラブルとして、以下のようなものがあります。
■湿気が多いと発生しやすいカーペットのトラブル■
- 汚れやすい
- カビ
- ダニ
- 臭い
カーペットは湿気を含むとホコリを吸着しやすくなります。
埃を放置するとカーペットが汚れてしまうだけでなく、ダニやカビの餌となってしまうため注意が必要です。
また、カビやダニは高温多湿で餌のある場所を好みます。
梅雨になるとカーペットにカビやダニが発生しやすくなるのは、湿度が高く、埃が付着しやすくなっているためです。
一般的にカビとダニは気温20~30℃、湿度70%以上でエサがある場所に発生しやすいと言われています。
雑菌が繁殖すると、カビが発生するだけでなく、悪臭が発生することもあります。
カーペットを衛生的に使用するためには、湿気対策をしっかりおこなうことが大切です。
カーペットの湿気対策

カーペットの湿気対策として、次の6つが挙げられます。
■カーペットの湿気対策■
- 室内の換気
- エアコンや除湿機の活用
- カーペットの通気
- カーペットの陰干し
- 除湿シートの活用
- 調湿性の高いカーペットを選ぶ
この章では、カーペットの具体的な湿気対策方法を詳しく解説いたします。
室内の換気

梅雨は雨が降る日も多いですが、お天気の良い日はできるだけ窓を開けて換気を行いましょう。
風通しを良くすることで、カーペットに含まれた湿気を逃がすことができます。
また、対面にある窓や扉の両方を開けておくことで、風の通りが良くなります。
お部屋の片側にしか開口部がない場合は、サーキュレーターで風を送ると良いでしょう。
湿気が溜まりやすい場所として水回りが挙げられますが、意外と寝室も湿気が溜まりやすいです。
寝室も朝は必ず窓を開けて換気することをおすすめします。
エアコンや除湿機の活用

カーペットにとって換気が大切ということは先程お話ししました。
では梅雨時や雨の日など、外の湿度が高い時はどのようにすれば良いでしょうか。
換気のために窓を開けても余計に湿度が上がってしまいます。
エアコンの除湿機能を利用して、カーペットの湿気を取り除きましょう。
除湿機をお持ちの方は、そちらを利用するのも一つの方法です。
除湿機の排熱で室温が上がることがありますので、暑くて湿度の高い時はエアコンを使用するか、エアコンと除湿機を併用することをおすすめします。
カーペットの陰干し

敷いたままのカーペットは裏面に湿気が籠り、カーペットの下のフローリングや畳にカビが生えることがあります。
お部屋の換気の他に、カーペットの陰干しも行いましょう。
カーペットを干す際は、毛足を傷めないよう裏向きにして干します。
カーペットに日光を当てると劣化や色褪せの原因になりますので、必ず日陰に干しましょう。
カーペットを干した時に、カーペットを軽く叩いて埃を落とすのも大切です。
埃やゴミを取り除くことで、カーペットの汚れやカビの発生を抑制します。
カーペットの通気

カーペットは裏面とフローリングの間に湿気がこもります。
陰干しができない大きなラグやカーペットは、裏返して裏面に風を当てましょう。
そうすることで、カーペットはもちろんカーペットの下のフローリングや畳のカビ・ダニ対策にもなります。
カーペットが大きくて裏返すことが難しい場合は、カーペットを半分に折り畳んで裏側に風を当てる方法がおすすめです。
またカーペットの下に椅子を差し込んで、サーキュレーターでカーペットの裏側に風を通すのも効果的です。
除湿シートの活用

カーペットの湿気対策には、除湿シートもおすすめです。
布団の除湿シートのように、カーペットとフローリングの間にこもった湿気を吸い取ってくれます。
限界まで湿気を吸うと効力を失ってしまうので、定期的に天日干しをしてこもった湿気を取り除いてください。
天日干しのタイミングを知らせてくれる吸湿センサー付きの除湿シートが便利です。
調湿性の高いカーペットを選ぶ

カーペットを購入される際に、調湿性のある素材を選ぶことも大切です。
■調湿性の高い素材■
- コットン
- ウール
- い草
コットンやウール、い草といった天然素材のラグは、梅雨時期でもサラッと快適にご使用頂くことができます。
この章では3つの素材の特徴をご説明します。
コットン

『コットン(綿)』は吸水性、通気性に優れている素材です。
繊維の中に空洞があるため熱が伝わりにくく、夏涼しく冬温かいという性質があるので年間通してお使い頂けます。
また、ふんわり柔らかく優しい触り心地ですので、赤ちゃんや小さなお子様がいるご家庭にもおすすめです。
コットンは耐久性にも優れておりますので、お洗濯ができるラグも多く、汗をかく暑い夏も衛生的にお使いいただけます。
ウール

『ウール』は羊毛からできている天然素材です。
ウールと聞くと冬のセーターが思い浮かぶかもしれませんが、実は梅雨や夏にもおすすめの素材です。
ウールは空気中の湿気を吸収する性質を持っています。
そのため湿度の高い日本の梅雨でも、ウールのカーペットはベタ付くことがなく、さらりとした感触を味わうことができます。
また、保温性、弾力性、自浄作用など、敷物として非常に優れた機能を備えています。
い草

畳や上敷きにも使われている『い草』。
高温多湿の日本にとって、い草の調湿作用は古くから重宝されてきました。
い草は調湿作用以外にも消臭作用や有害物質の吸着作用もあります。
近年畳の部屋は減りつつありますが、フローリングの上にい草ラグを敷くことで、湿気の多い季節もべたつかず快適に過ごすことができます。
置き畳などを活用して、リビングの一角に和室スペースを設けても良いでしょう。
カーペットのカビ予防方法

この章では、カーペットのカビを予防する方法をご説明します。
普段のお手入れ
カーペットを敷いているお部屋は、週に2回を目安に掃除機を掛けましょう。
使用頻度の高い部屋のカーペットは、できるだけより高頻度で掃除機を掛けることをおすすめします。
カーペットの毛並みを起こすように掃除機をかけてください。
毛足の根元に入り込んだゴミを取り除き、カーペットの毛足に含まれた湿気を取り除くことができます。
また先程の章でもお伝えしたように、普段からお部屋の換気やカーペットの通気を行うことも大切です。
お部屋の換気は、毎日湿度が低い朝と夕方に行い、風通しは月に1~2度行いましょう。
陰干しは半年に1回湿度の低い季節を選んで行います。
詳しいお手入れ方法は、こちらの記事をご覧ください。
重曹を使ったお手入れ

最近お掃除アイテムとして、よく登場する重曹。
弱アルカリ性の重曹は皮脂や汗、食べこぼしといった酸性の汚れを中和する作用があります。
また、酸性の臭い成分を中和し消臭効果も発揮します。
重曹には吸湿性もあるので、カーペットの湿気対策にも効果的です。
ご使用方法として、重曹水を作りスプレーする方法と、粉をそのまま撒き、しばらく置いた後掃除機で吸い取る方法があります。
重曹を使った詳しいお手入れ方法は下の記事でご覧ください。
抗菌防臭ラグ・カーペットを選ぶ

予め抗菌防臭のラグを選んでおくことで、湿気の多い時期も清潔で衛生的に過ごすことができます。
抗菌防臭加工が施されているラグは、菌の繁殖を抑え、カビや臭いの発生を抑制する効果があります。
カーペットにカビが発生したときの対処法

カーペットにカビが発生したときは以下の手順で対処しましょう。
- カビを除菌する
- 染み抜きをする
まずカーペットの除菌をし、それから染み抜き行います。
①カビを除菌する

カーペットにカビが発生したときは先に消毒用エタノールを使って除菌を行います。
カビの除菌の手順は4つのステップで進めていきましょう。
- カーペットとその周辺に消毒用エタノールを吹きかける
- 15分ほど置いておく
- 清潔な乾いた布でエタノールを拭き取る
- ドライヤーでしっかり乾かす
ただし、消毒用エタノールはカビを除菌することはできても、一度汚れてしまったシミを落とすことはできません。
次の項目では染み抜きの方法を説明いたします。
②染み抜きをする

カビの除菌を済ませたら、今度はカーペットについた黒いシミを消しましょう。
染み抜きは以下の手順で行います。
- ぬるま湯に酸素系漂白剤を溶かす
- 1で作った漂白剤液をシミに塗布する
- 10分ほど置いておく
- 雑巾で水拭きをして漂白剤を拭き取る
- 乾拭きで水分を取る
- ドライヤーでカーペットをしっかり乾かす
塩素系漂白剤は漂白力が強い分、カーペットの色褪せや毛足の傷みが発生することがあります。
漂白剤を利用する際は、塩素系ではなく酸素系をご使用ください。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
湿気対策におすすめのラグ・カーペット

この章では、湿気対策におすすめのラグ・カーペットをご紹介いたします。
ソフティ

ソフティは抗菌防臭加工に加えて、防ダニ加工も施されたラグです。
洗濯機のご使用が可能ですので、高温多湿の汗ばむ季節でも、清潔な状態にしておくことができます。
またこちらのカーペットはお手入れのしやすさに加えて、耐久性もあり日常使いに適しています。
明るいホワイト系のお色がより一層清潔感を感じさせてくれます。
リベルテ

リベルテは、化学薬品を使用していないオーガニックコットン100%のラグです。
手摘みで選別された良質で希少な『サマルカンダリア』という綿を使用。
サマルカンダリアは一般的なコットンより、繊維が長く毛羽立ちが少ないので、滑らかな手触りなのが特徴です。
素肌に優しい肌触りなので、お肌の敏感な小さなお子様でも安心。
また表面がサラッとしているので、じめじめした梅雨や汗ばむ夏も気持ちよくお使い頂けます。
洗濯機でのお洗濯はもちろん、防ダニ加工も施されていますので、お取り扱いしやすい商品です。
バロー

バローはウール本来の自然な色を活かした、サイズオーダーができる国産カーペットです。
ナチュラルな色と風合いが、どのようなインテリアとも相性が良く、シンプルで飽きがきません。
また、ウール100%ですので吸湿性に優れており、汗ばむ季節でもべたつかずに気持ちよく過ごすことができます。
高密度で踏み心地が大変よく耐久性もありますので、ぜひ長くお使い頂ける商品です。
ウールリース

ウールリースは無染色のウールを使用しています。
無染色とは羊の毛の脱色や染色を一度も行っていないということを指します。
そのため、羊毛があまり傷んでおらず本来の艶や滑らかな質感を感じることができます。
また無染色ウールは、染色をしているウールよりも吸湿性が高く、断熱性・保温性が高いです。
そのため夏涼しく冬温かくお過ごしいただけます。
繊維に油分もたっぷりと残っているため、水分や汚れを弾きやすく汚れにも強いです。
素材の素晴らしさはもちろん、おしゃれで可愛い印象を与えてくれるウールリース。
ホワイトインテリアや、ナチュラルテイストのインテリアのアクセントに是非取り入れて頂きたいラグです。
メロア

メロアは綿素材のベロア生地を使った、夏を爽やかに過ごすことができるラグです。
本来は吸水性が低いベロア素材を綿100%にすることで、ラグの吸水性を高め、汗をかきやすい季節もベタベタせずに過ごせるようにしました。
ベロア素材ならではの光沢と滑らかな手触りは、ラグに高級感を与えお客様をお迎えするリビングにもお使い頂けます。
また、小さなお子様のおられるご家庭にもおすすめのふわふわのキルト生地となっております。
洗濯機でのお洗濯が可能ですので、お手入れもしやすく夏でも清潔にご使用頂けます。
オアシス2

オアシス2は抗菌防臭・防ダニ加工が施されており、梅雨の季節でもカビやダニの心配がいりません。
また手洗いでのお洗濯が可能ですので、お手入れのしやすさもおすすめです。
「TPRM8」という清涼加工剤が施されておりますので、暑い季節は涼しく感じます。
湿度が高く、じめじめした季節でもサラッと爽やかにお使い頂けます。
本記事のまとめ
本記事では、カーペットの湿気対策について解説いたしました。
カーペットに湿気がこもると、ダニやカビが繁殖する可能性があります。
特に、梅雨から夏は高温多湿で、よりダニやカビが繁殖しやすくなります。
カーペットとフローリングを清潔に保つためにも、湿気対策を徹底しましょう。
カーペットの湿気対策方法は以下の通りです。
- 室内の換気
- エアコンや除湿機の活用
- カーペットの通気
- カーペットの陰干し
- 除湿シートの活用
- 調湿性の高いカーペットを選ぶ
万が一カーペットにカビが発生した時は、除菌とシミ取りをおこなってください。
ウールや綿など、調湿性の高い素材のラグを選ぶことで、汗ばむ季節も快適にラグの上でお過ごしいただけるでしょう。
合成繊維のラグはカビやダニに強く、衛生的に使いやすいです。
高温多湿な日本だからこそ、カーペットの湿気対策は念入りにおこないましょう。